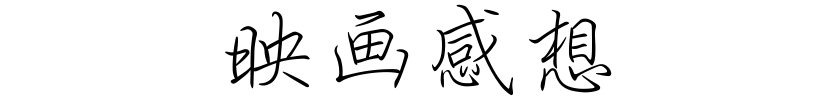- 1955年大映映画 6/23NFC
- 監督:溝口健二 脚本:川口松太郎
- 撮影:杉山公平 音楽:早坂文雄
- 出演:京マチ子/森雅之/山村聰
助監督に増村保造が付いているが、その増村保造はこの映画を失敗作だと評価している。
増村保造は溝口健二を論じるのに、谷崎潤一郎とパラレルに論じた。
両者とも東京の下町文化の中で育ち、その文化に洗礼されながら、関西文化に惹かれるように関西に移り住んだ。増村保造は両者が関西文化に惹かれたのは「女」故だと主張する。両者とも「女」を描いた作家だ、「女」の情念を描くには関東文化はあまりにもあっさりとし過ぎている、「女」の情念に導かれるようにして両者は濃密な関西文化に赴いたのだ。そう増村保造は論じる。
この映画は通俗メロドラマであるが故に、「女」はけっして濃密に描かれていない。「女」の情念はむしろあっさりと描かれている。だからこそ増村保造は失敗作だと決めつけたのだが、僕は心を動かされた。
濃密な関西文化は『地獄門』でも素晴らしい撮影をしている杉山公平が作り出す色彩美の中に生きている。揚貴妃が近衛兵たちの手で殺されるとき、地面に落される宝石類を捉えるクロース・アップは特に心に残る。そのような関西文化的あでやかな色彩美の中で描かれるのは「女」であるよりは、ある悲しみなのだ。
二人の男と女が出会う。男は心から愛するものを失った悲しみを抱えて生きていて、女は自分を単なる道具として扱っている家族の中で愛情を得られない悲しみを抱えて生きている。その悲しみはおそらくは溝口健二が終生抱えていただろう悲しみだ。
二人の悲しみが共鳴するシーンはとても美しい。
祭の日、身分を隠して人混みに紛れる男と女。二人は祭の人々に酒を勧められ、芸を披露することを促される。男は楽器を弾き、女は舞う。薄い水色の衣装を身に纏った女の踊りは豪快でいて繊細だ。疲れた二人は祭の後の静けさの中でお菓子を口にしながら、お茶を飲む。お前とはずっとこうして一緒に生きてきた気がする。男の言葉に女は頷く。二つの悲しみが共鳴しながら、心に染みる音楽を作り出す。
僕が心を動かされたのはそのような悲しみが厳格な古典主義で描かれているからだ。ここでは悲しみはいわば突き放されている。監督はけっして悲しみに寄り添わない。それは溝口健二が悲しみを救うことはできないことを身をもって知っていたからではないだろうか。人ができるのは悲しみを見つめることだけなのだ。
僕はこの映画を観て溝口健二が本当に好きになった。
1999/06/23